前照灯も、前作の尾道分と次作分を含めて合計10個。
楽しい筈の趣味もロット作業では楽しくなくなります。
と言う事で、現状逃避の筈だったパワーパックも2個作成したために難行苦行。
こうなると、エイヤと粗造りで切り抜けたい所です。
2015.6.4

左から、
プチ電車の車体を利用したN700、
前作・尾道鉄道、
淡路交通(元・南海)、
京阪・びわこ号、
井笠鉄道・DC+PC編成
です。
当初、日の丸、別府、北但、北恵那なども候補に上がっていましたが、今回は比較的新しい時代の、流線型車両から選択しました。
2016.6.1

井笠のホジは笠岡駅最寄に現車が保存されていて、本物の見学から開始しました。
デッキはスイテ49のそれと極めて似ています。
びわこ号は集電ポールを付けます。
旨く集電できるかどうか不安です。
淡路交通は木製車体の縦スリット+Wルーフ+Zパンタと言う事で、拙鉄では標準仕様です。
尾道は前作です。
N700は唯一プチ電車の車体を利用した物です。
楽勝と考えていたのですが、中間車の車長を短くする、車体幅の狭さ対策など、意外に苦戦=楽しめています。
2015.6.1

上から
1)井笠鉄道の気動車
2)淡路交通の電車
3)京阪・びわこ号
と言う事で、クラフトロボで窓抜き、板を重ね貼り、サーフェーサーと進んだ所です。
2015.2.15
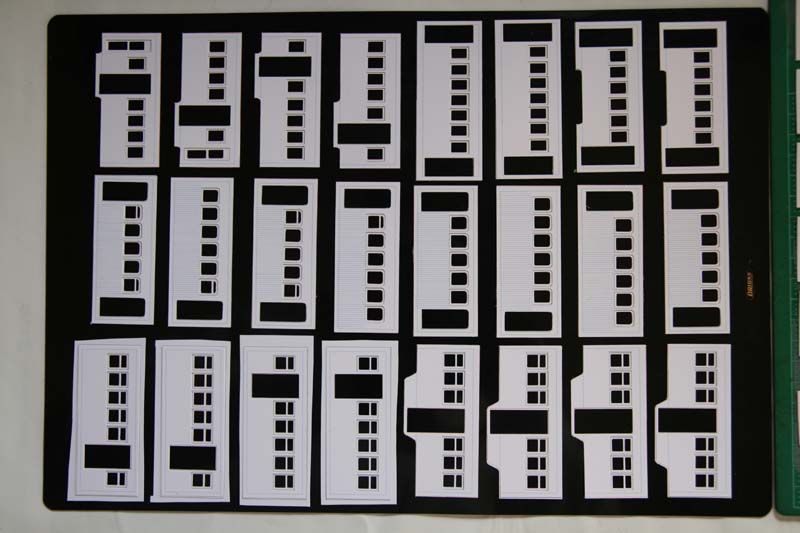
淡路交通の電車は、正面5つ窓、Wルーフ、窓の上辺が丸いタイプで4両編成です。
京阪・びわこ号は、鉄道線のドア付車両、軌道線のドア付車両で、4両編成です。
これ以外に、プチ電車の車体を利用したN700の編成を作成中です。
2015.2.15
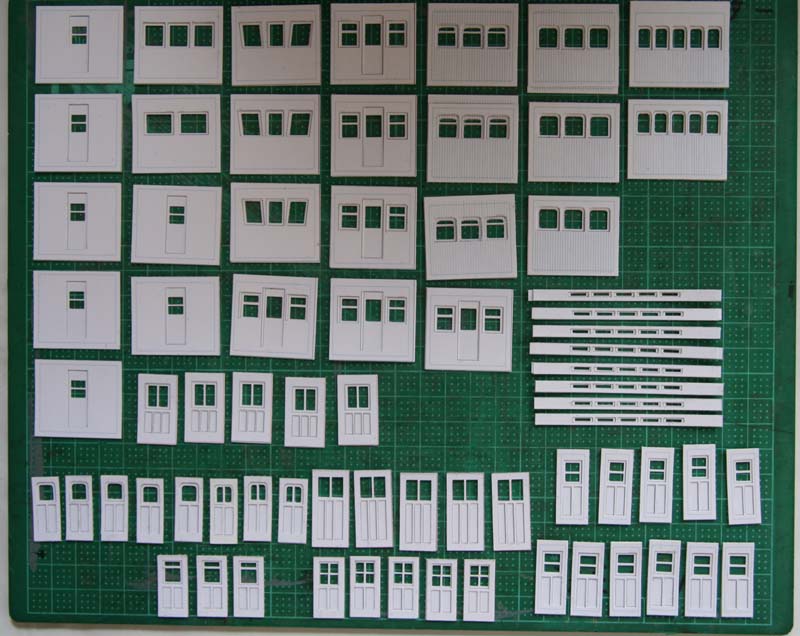
2軸車の選択は必然で、プチ電車の動力利用は丁度この条件に合致し、しかも廉価。
廉価と聞くと昔取った杵柄(ISO9000)で、安い、早い、高品質を追求したくなります。
そうなると、大量生産技術の確立が必須。
先ずは16両/1ロットで試作しています。
予算目標は1編成=4両=2,000円以下です。
2015.01.03
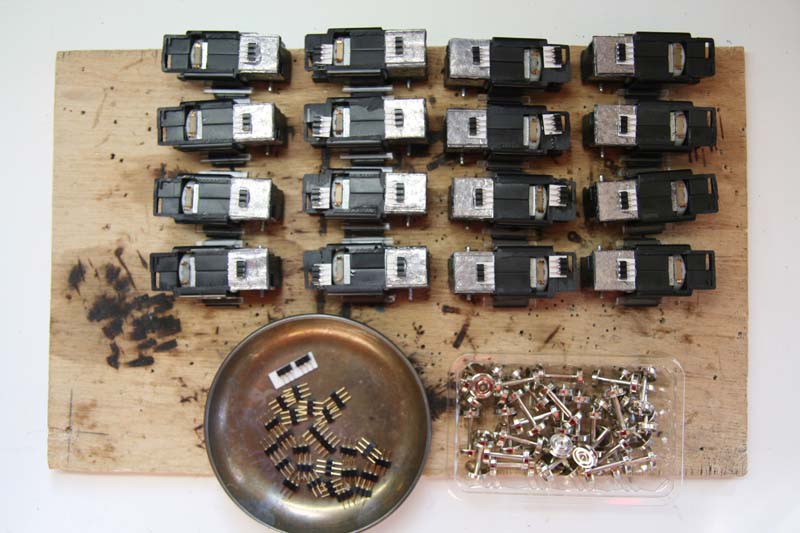
プチ電車のモーターは3V定格と想定されるので、4モーター直列で12V定格を目指し、4両編成で作成しました。
Zパンタは自作、集電機能を有しています。
室内灯は一応装備していますが、安物のLEDで、しかも1灯/両と倹約したため、拙鉄基準には満たない暗さです。
2014.12.31

車両間には母線2本、モーター直列接続用の1本を合わせて、合計3本の線が渡っています。
これが曲線走行には大変な曲者で、見かけを無視して機能本位で実現しました。
車体はクラフトロボ利用のペーパー3枚重ねです。
2014.12.31

と言う事で、気を良くして更に4編成(16輌)を追加作成することとしました。
作成予定候補は、花巻、京都N電、日の丸交通、下電です。
2014.12.21

Zパンタは架線集電可能な物として自作しました。
車両間には3線(母線2本とモーター直列接続線)が渡ります。
動力は勿論プチ電車です。
2014.12.21

車両は撮影の為に仮に乗せたもので、架線集電対応の物をこれから作成予定です。
森の中の物置小屋の中に車両検知センサーを組み込んであります。
車両を検知すると速度を落とす仕組みです。
ストラクチャーはN用を利用しました。
レイアウトもこれだけ小さいと、HOサイズではバランスが取れません。
今回はヨーロッパ調で纏めてみました。
2014.12.01

線路の内側のスペースに、スケルトン(屋根なし)の点検庫を作ることにしました。
独立した直線線路では面白くないと言う事で、点検庫の入口側は本線との平面クロス(ダミー)を設置。
このターンテーブルはLPレコードプレーヤーなので、LPレコードの中心を決める軸が出ています。
最初は切取る予定でしたが、レコードプレーヤーの雰囲気を残す意味でこの軸を残すことにしました。
そうなると中の線路と干渉するので、線路を中心から少しずらせました。
架線は今回はさすがに曲線型にしました。
写真の太い線はカテナリー線です。
この下に細い架線を吊り下げる計画です。
2014.8.2
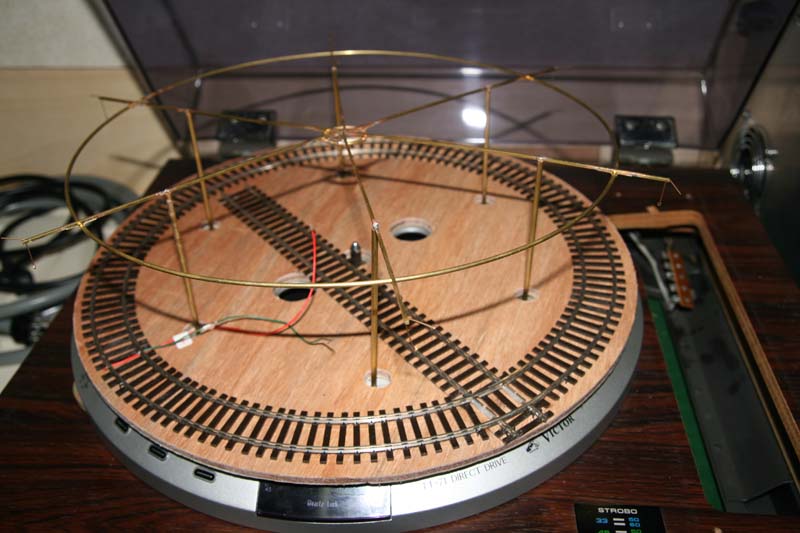
これに線路を敷設、ターンテーブルを逆回転、このターンテーブル上の線路を車両が走ると止まっている様に見える筈です。
と言うコンセプトのレイアウトを作成中です。
写真の車両はプチ電車の動力を利用した3両連接車ですが、台枠のみ(写真の状態)なら旨く走ってくれました。
車体を乗せると内側が干渉して脱線します。
2014.7.30
